数学のカリキュラムの最後に東大数学の過去問演習があります。
東大数学はかなり難しいですが、すべての問題が難しいというわけではありません。
理系なら6問、文系なら4問中から簡単な問題を見つけだして、なんとか半分以上得点することが重要になってきます。
このページでは赤門アカデミーでどのように東大数学の過去問演習を指導しているのかについて解説していきます。
東大数学の過去問に手を出す前に
東大数学の過去問に手を出す前に、必ずこなさなくてはいけない参考書があります。
東大数学が解けるレベルに実力がなっていないのに、過去問演習を始めてもあまり意味がありません。
ここでは、最低限こなしておかなければいけない参考書、問題集について解説していきます。
まず、絶対にやらなければいけない参考書は青チャートやFocus Goldなどの網羅系参考書です。
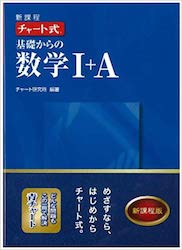
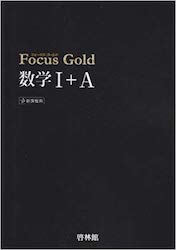
これらの、参考書の例題は少なくともすべて、一瞬で解法を説明できるようになっていなければいけません。
特に理系は数3まであり、かなり膨大な量になりますが、網羅系参考書の例題の解法を基にして、入試問題は解いていくので、例題の解法が頭にないとそもそも入試問題が全く解けません。
これは、英単語をやらずに、難関大学の長文問題を解くことと同じことです。
なので、最低限、網羅系の参考書の例題の解法が頭の中に入っていることが東大数学の過去問演習を始めるための必要条件になります。
また、網羅系の参考書を仕上げた後には、過去問に入る前に実践系の問題集を仕上げる必要があります。
実践系の問題集とは、網羅系参考書で定着させた解法をより実践的な入試問題で使えるかどうか訓練するための問題集です。
具体的に挙げますと、一対一対応、やさしい理系数学、良問のプラチカなどといった問題集です。
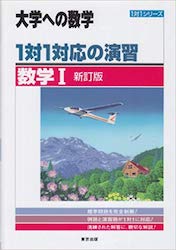


よほど本試験までの時間がない生徒さんは、網羅系の参考書が終了次第すぐに過去問に入ってしまいますが、ほとんどの生徒には、一度これらの実践系の問題集を解いてもらった上で過去問に入ります。
また、さらに時間のある生徒さんには、実践系問題集でももう1段上のレベルの新スタンダード演習、ハイレベル理系数学などを解いてから過去問に入ります。
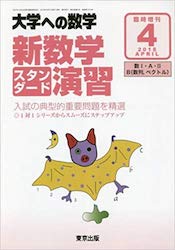

このようにして、いきなり過去問に入ってもただ限られた数しかない過去問を消費してしまうだけです。
なので、一般的な生徒さんのカリキュラムでは網羅系参考書を仕上げた上で、実践系問題集の演習を積んで過去問に入ります。
最低限、網羅系参考書は仕上げた上で東大の過去問を解くようにしましょう。
また、網羅系参考書の演習、実践系問題集の演習については、以下のページを参照してください。
一対一対応、やさしい理系数学など、数学の実践系問題集の使い方
東大数学過去問演習で使う参考書
次に東大数学の過去問演習で使っていく参考書について解説していきます。
東大数学では時間がない限りは基本的に25~7年分の過去問を解いていきます。
なので、東大の過去問が27年分載っている赤本の「東大数学27ヶ年」もしくは通称青本と言われている、駿台出版の「東大入試詳解25年数学」のどちらかを使います。

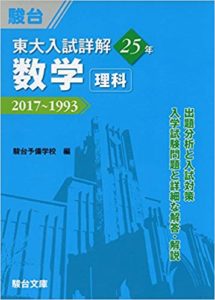
赤本の方が2年分多く掲載されており、なおかつA~Dのランクで問題の難易度が分けられています。
この各問題に書かれている難易度がかなり重要になってきます。
なので、基本的に赤本の方を使って過去問演習をしていきます。
ただ、青本にも様々な解法が載っていたりするので、両方持っておくのがベストです。
東大数学過去問演習の進め方
次にここでは、東大数学の過去問演習を赤門アカデミーではどのように進めているのかについて解説していきます。
生徒さんの本番までの時間や実力によってスタートするところや実際に解いていく年代などが異なりますが、とりあえず27年分全て演習する余裕のある生徒さんのカリキュラムについて解説していきます。
まず、27年分を演習する場合、新しい10年分と古い17年分とで分けて演習します。
まずは、古い17年分を27年前のものから順番に解いていきます。
この17年分に関しては、特に時間を測らずじっくり解いてもらっています。
昔の問題の方が遥かに難しいので、難易度に慣れるということとじっくり考えると言うことを身に付けてもらいます。
その中でも難易度がAのものは必ず解答を見ずに解けるようにして欲しいです。
できればBの問題も解ければなお良いです。
このように難しい問題の中にも自分が解ける問題があるということを体感していくことが重要になります。
解けなかった問題、間違えた問題については今までの網羅系参考書の演習から行っている方法と同じ方法で復習していきます。
詳しくは以下の記事を参照してください。
この17年分が終われば、新しい方の10年分を解いていくことになります。
これは、本番の試験をイメージして理系であれば150分、文系であれば100分時間を測って演習をします。
そして、実際に採点して点数を出していきます。
この際にA, Bの難易度がついている簡単な問題は必ず計算ミスなく解けるようにしましょう。
また、解けなかった問題も時間があれば考えて解く時間も1~2時間程度は設けるのが理想です。
この過去演習をするにあたって注意しなければならないことが2点あります。
まず必ず過去問は年度別にまとめて演習することです。
通常赤本や青本は年度別ではなく分野別で問題が並べられています。
しかし、東大数学において最も重要になってくるのが各問題の難易度の判別です。
東大数学では全ての問題が難しいというわけではなく、簡単で解きやすいといわれる問題が必ず半分程度は入っています。
そして、東大数学では5割得点することができれば合格点としては十分です。
なので、この簡単で解けそうな問題を実際に探して、正確に解いていくことが重要になります。
つまり年度別で必ず並べて難易度の比較をすることが重要なのです。
ほとんどの生徒には自分で紙に書き写してもらうか(問題の年度別対応表は赤本の後ろに載っています。)、年度別に問題がまとめられているサイトを見ながら演習を進めます。
過去問演習をやる際は分野別ではなくて、年度別で行うようにしましょう。
また、A, Bと難易度のついた問題は必ず正確に答えまでたどり着くよう細心の注意を払って解きましょう。
京大はまだ答えがまちがっていても多少の点数はきますが、東大に関しては答えが計算ミスで少しでも狂うとほとんど点数がきません。
東大数学の一問あたりの点数は20点です。
この20点は合格最低点から平均点までの差とほぼおなじくらいになります。
つまり、この20点を落とすことで、定員の半分くらいは順位が下がります。
最初のうちはAだけでもいいので絶対に答えまで正しい計算をしてたどり着くようにしましょう。
だんだんB問題も解けるようになってきて、新しい10年分を時間内に演習する際はA, B両方が完答できるようになるのが目標です。
また、直前期に解く問題として、新しい10年分の中から、2、3年分は残しておくことをお勧めします。
東大数学の過去問演習での確認テスト
次に赤門アカデミーでの東大数学の過去問演習での確認テストについて解説していきます。
東大数学の演習に入ると全ての過去問を指導内にテストし、チェックすることはかなり難しくなります。
なので、60分や90分事前に時間を設けて、解いたことのない年度の過去問をやって、そのうち簡単な問題が1問でも解けないかチェックしていきます。
つまり、普段の家での演習の一部を指導のテストとして行うということです。
この指導の際にチェックしていきたいのが、今まで解説してきた難易度判定と解答の記述です。
解答の記述は第三者にチェックしてもらわないと、自分の記述の欠点や改善点などが見つけられません。
なので、時間が測られている中で、書くべき記述は書かれているか、論理的に説明できているか、グラフや図や必要であればかけているかなどをチェックしてきます。
また、もう一つ重要なのが、字が丁寧にかけるかどうかです。
当たり前のことといえば当たり前なのですが、数学が得意で頭の回転が早い生徒さんのうち一定数はかなり字が丁寧ではなく、読めない文字も存在する解答を書く人もいます。
数学の答案は白いスペースに自分で記述していくので、字が丁寧でないとかなり採点しづらい印象を与えます。
読めない文字については下手をしたら、採点してもらえない可能性も出てきます。
白い紙のスペースにしっかりと丁寧に自分の解答が記述できるかどうかチェックしていきます。
また、指導時間以外で答案を添削して欲しい場合は別途添削代がかかってきます。
東大数学の過去問が無くなったら
東大数学の過去問は27年分もありますが、カリキュラムの進みが良い生徒さんですと、高3の夏休みや10月あたりで過去問が無くなってしまったという人も出てきます。
そのような人には、さらに東大模試の過去問演習をしてもらっています。
東大模試の過去問については、河合の東大オープン模試、駿台の東大実戦模試がそれぞれ販売されています。
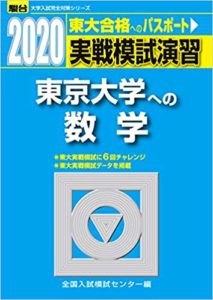

これらを購入して過去問演習と同様に進めてもらいます。
駿台は、簡単な回、難しい回があったりと難易度のばらつきが多いですが、河合が比較的標準な難易度になります。
どちらも本番の良い練習になるので時間のある方は試してみてください。
また、これらでも足りないという生徒さんには、メルカリやヤフーオークションなどで、さらに昔の東大模試の過去問や、東進の東大本番レベル模試の過去問も購入して進めてもらいます。
東進の東大本番レベル模試の数学はかなり難しいのでさらに上のレベルの問題を解きたいと言う生徒さんむきです。
ただ、本番では簡単な問題も出題され得るということと、点数が低すぎて落ち込まないということが重要になります。
特に直前期は精神的に不安定になりやすいので、東進の過去問や駿台の難しい過去問の点数が悪くて、無駄に落ち込まないようにしましょう。
まとめ
以上が赤門アカデミーでどのように東大数学の過去問演習を進めていくかについての解説です。
まずは、過去問演習に入る前に仕上げるべき参考書を仕上げてから入りましょう。
過去問演習が始まったら、難易度の比較的易しいA, Bのついた問題を落とさないよう細心の注意を払って演習していきましょう。
この演習を最後までこなせば、東大数学に関してはほぼ合格点が取れるようになります。
以上のような注意事項をよく守って演習していきましょう。
